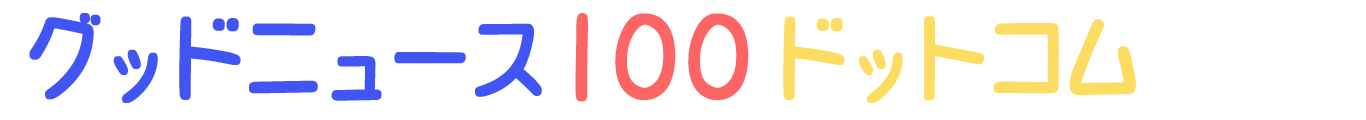毎年3月と9月にやってくる、お彼岸。
あなたの家庭では、おはぎやぼたもちを作ったり、食べたりしますでしょうか?
私、かけらの家では、春も秋も、小学生の時に父親から、
「お彼岸だから、こしあんのおはぎを買ってきて」
と、言われていたので、お彼岸には、こしあんのおはぎを食べるものだと、大人になるまで、ずっとそう信じていました。…(^^;)
一方、ぼたもちって、夏休みのお盆で、田舎の実家に帰ると、伯母さんが、
「ぼたもち、食べな」
と言って、大きなつぶあんや、きな粉のぼたもちを、食事として食べていたので、ぼたもちとは、大きくて、つぶあんだと、ずっとそう信じていました。…(^^;)
でも大人になってから、知識も増えて、
「春、牡丹の花が咲くから、ぼたもちで、秋、萩の花が咲くからおはぎ」
だと、初めて知った時は、ビックリしてしまいました!
でも、それって本当なの?
と思ってしまったので、今回は、おはぎとぼたもちの違いと、なぜこしあんとつぶあんの2種類があるのか?などについて分かりやすく解説します。
おはぎとぼたもちで大きさは違うの?

食品加工技術が進んだ現代では、お店で売っているおはぎやぼたもちの大きさは、特に変わりませんし、こしあんとつぶあんと、両方あるので食べることが出来ます。
けれども、おはぎやぼたもちの起原は古く、江戸時代の元禄年間の書物にも、書かれているのです。
なので、もともと、牡丹の花に似せて作られた、ぼたもちは大きく、小さい萩の花に似せて作られた、おはぎの方が、本来は小さかったのです。
・・・と、いうわけで、あながち私、かけらが信じていたことも、当たらずとも遠からじ、だったのです!…(^^;)
なぜ、こしあんとつぶあんがあるの?
前述したように、おはぎやぼたもちは、江戸時代から作られていたので、現代ほど、食品の保存技術が、発達していませんでした。
なので、秋に収穫されたばかりのアズキは、皮も柔らかいので、つぶあんとして、おはぎに使われていました。
一方、春のアズキは、半年近く保存されたものだったので、皮が硬いので除いて、こしあんとして、ぼたもちに使われていました。
・・・と、いうわけで、私、かけらが信じていたこととは、まるっきり逆だったので、衝撃の真実でした!…(^^;)
夏や冬のおもちは無いの?
現代では、おはぎやぼたもちは、お彼岸の時にだけ、食べられるお供物とされています。
けれども、もともと、ご先祖さまに感謝するのは、夏や冬にもあったようで、似たようなおもちが、食べられていました。
夏に食べるおもちは「夜船(よふね)」といって、冬に食べるおもちは「北窓(きたまど)」と、呼ばれていました。
この名前の由来なのですが、記事中の動画「おはぎ/ぼたもちレシピ」を観てもらえば、分かるかと思います。
つまり、おはぎやぼたもちの、おもちの部分は、ふつうのおもちのように、臼と杵で、ペッタン、ペッタン、つきません。
なので、ご近所の人が「いつ、ついたのか分からない」ことから「つき知らず」と呼ばれるようになりました。
これが、言葉遊びで、夏の夜に着いた船は、いつ着いたか分からないことから、「着き知らず」となり「夜船(よふね)」と呼ばれるようになりました。
一方、冬の夜の北側の窓には、月が見えずに分からないことから「月知らず」となり「北窓(きたまど)」と呼ばれるようになったのです。
おはぎやぼたもちの作り方とは?
それでは、お約束の「おはぎ/ぼたもちレシピ」の動画をご紹介します。
あなたも、この動画を観て、ご家庭で手作りの、おはぎやぼたもちを作ってみて下さいね!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように、おはぎやぼたもちの違いや、こしあんとつぶあんの違いには、様々な意味があったのです。
けれども、どちらも、ご先祖様に感謝する気持ちは、一緒です。
あなたも、これを機会に、ぜひ、お墓参りに行ってみてはいかがでしょうか?