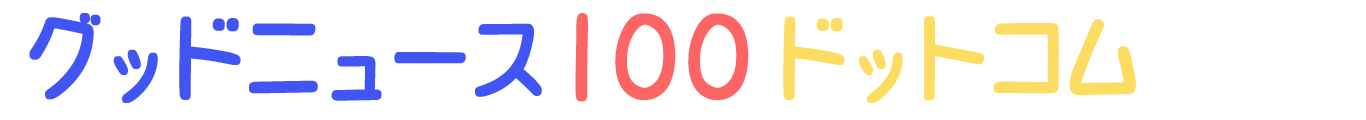毎年7月末には、土用の丑の日がやってきて、うなぎを食べる習慣があります。
でも、あなたは、この発案者が誰で、由来や理由を知っていますか?
私、かけらは全く知らなかったので、調べてみてビックリしてしまいました!
だって、意外と有名な日本の発明家だったからです。
私とうなぎとの思い出は古く、小学生の頃までさかのぼります。
今でもそうですが、当時うな重やうな丼は、高級な食べ物で、1年に1回か2回位しか、食べることが出来ませんでした。
けれども、私が中学一年生の夏に、兄と妹と、一家5人で最後の海水浴に、静岡県の浜名湖に行ったんです。
当時も浜名湖は、うなぎの養殖で有名でした。
そこで、私は、
「わーいわーい!うな重が安くて、たくさん食べられる!」
そう思って、新幹線の浜松駅を出て、すぐ近くのうなぎ屋さんに入ったのです。
ところが・・・。
まずはじめに、値段なのですが、決して安くはなく、当時の東京の相場と同じ、1,200円位と高かったのです。
あとは、出てきたうな重の、うなぎの大きさや、美味しさも東京と同じ程度だったので、ガッカリしてしまった、私だったのでした。
そこで、今回は、土用の丑の日の紹介と、発案者は誰なのか、なぜ、うなぎを食べるのか、その由来と理由などについて分かりやすく解説します。
土用の丑の日とは?

まずはじめに「土用」ですが、これは古くから伝わる「五行」に由来する暦の雑節で、1年のうち4つの期間の直前に、約18日間ずつあります。
次に「丑の日」ですが、これは十二支の1つで、この「土用」の期間のうちに、1日か2日存在しています。
・・・というわけで、土用の丑の日とは、明治以前の太陰暦で、決められていた別に特別では無い、ある1日のことだったんですね!
土用の丑の日の発案者は誰なの?
これは、前述したように、太陰暦で使われていた、ある特定の日を指しますから「古代の人」としか、答えられません。
・・・というわけで、土用の丑の日そのものの、発案者という特定の個人は、誰にも分からないのです!
土用の丑の日にうなぎを食べる発案者は誰なの?
これは、江戸時代の学者であり、発明家の、
「平賀源内である」
という説が、最も有力視されています。
・・・というわけで、平賀源内は、作詞家であり、作曲家でもあり、コピーライターでもあり、医者でもあり、エレキテルを作った、発明家でもあったんですね!
土用の丑の日にうなぎを食べる由来とは?
これは、正式に書面で残っているわけでは無く、どのような書物にも書き残されていないので、口頭伝承で、庶民の間に広まった以下のお話です。
江戸時代に開業した、とある、うなぎ屋さんが、特に夏にうなぎが売れなくて、困ってしまい、平賀源内先生の所に行って相談しました。
すると、平賀源内先生は、
「本日丑の日、と紙に書いて、店先に貼りなさい」
と言ってくれたので、言われた通りにすると、うなぎが売れて、大繁盛したので、他のうなぎ屋さんたちも真似をすると、同じく大繁盛しましたとさ…。
・・・というわけで、土用の丑の日にうなぎを食べる由来は、平賀源内の一言だったんですね!
土用の丑の日にうなぎを食べる理由とは?
これは、諸説あって、ハッキリとした理由は分からないのですが、江戸時代の庶民の間では、
「夏の丑の日に、う、で始まる食べ物を食べると、夏負けしない」
という、都市伝説が、存在していたらしいのです。
なので、うなぎに限らず、馬の肉、牛の肉、うさぎ、うどん、梅干しなどを、好んで食べていたそうなんです。
・・・というわけで、平賀源内は、博学だったので、この都市伝説を上手く利用して、うなぎ屋さんに「本日丑の日」と書かせたのかもしれないワケです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
このように、土用の丑の日の発案者は誰なのか、なぜ、うなぎを食べるのか、その由来と理由などについては、諸説諸々とあるのです。
あなたも、土用の丑の日には、美味しいうなぎを食べて、暑い夏場を乗り切って下さいね!(^^)